2025/07/30
日常の中にいる「支援職」の存在
社会においては、必ずしも「心理職」や「相談員」という肩書きではなくとも、業務の中で人の話を聞いたり、相談に乗ったりする機会が多い方がいらっしゃいます。たとえば、学校の先生や地域包括支援センターの職員、介護現場のケアマネジャー、企業の人事担当者や管理職など。こうした方々は、日々「人の困りごと」に向き合いながら、サポートや助言を求められる立場でありますので、広い意味で「支援職」と言えるのではないでしょうか。
支援に必要な「見立てる力」と「問題解決力」
支援職として人をサポートする際にとても重要なのが、「見立てる力」と「問題を解決する力」です。つまり、目の前の相手が今どのような困難を抱えているのかを的確に捉え、その背景にある構造を見極め、効果的な支援方針を立てられるかどうかがカギになります。
この「見立てる力」と「問題解決力」の精度を高めるために、大いに役立つのが認知行動療法(CBT)の知識と実践力です。
認知行動療法とは?
認知行動療法は、出来事・思考・感情・行動のつながりに着目し、現実的かつ具体的に問題を整理し、改善へと導く心理療法です。海外はもちろん、日本国内でも数多くの研究が行われており、エビデンスに基づいた信頼性と妥当性の高い方法として、精神医療はもちろん、福祉、教育、ビジネス領域など幅広く用いられています。
認知行動療法を学ぶ:「CBT資格認定講座」
目白心理総合研究所では、提携機関である「Room Turn Blue」と連携し、「CBT資格認定講座」を開講しています。この講座では、谷口知子理事長著『認知行動療法[ベーシック]』(金子書房 2021年)をテキストに用い、認知行動療法の基礎的な理論と技法を段階的に学んでいきます。受講方式はオンラインまたは対面を選ぶことができます。
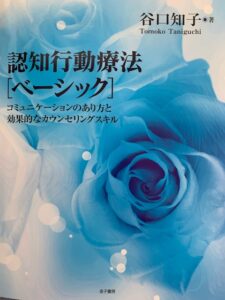
現場で“使える”スキルとしてのCBT
特にこの講座の特長は、「現場で使える」知識とスキルを重視している点にあります。まずCBTの理論を学ぶ前に、クライエントの話に注意深く耳を傾け、理解しようと努めるコミュニケーションスキル(傾聴スキル)を習得し、クライエントとの信頼関係(ラポール)を築くための重要性を学びます。次にCBTの理論や技法を学ぶだけでなく、ロールプレイ演習を通じて実践力を養い、実際の支援現場で活かせる力を身につける構成となっています。
CBTの理解が深まることで、クライエントの話を傾聴した上で「考え方の癖」や「行動パターン」に焦点を当てた「見立て」が可能になります。また、支援者自身の感情や考えを整理するツールとしても役立ち、支援の質が大きく向上します。
支援力をもう一段階深めたい方へ
「相談を受けることが増えてきた」「何となく対応しているが、自信が持てない」と感じている支援職の方にこそ、認知行動療法のコミュニケーションの学びはおすすめです。基礎から丁寧に学ぶことで、支援の確度と自信が高まっていくはずです。
Room Turn BlueにおけるCBT資格認定講座は、2025年10月より後期スケジュールがスタートします。ご興味のあるかたはぜひ下記URLからお問い合わせください。